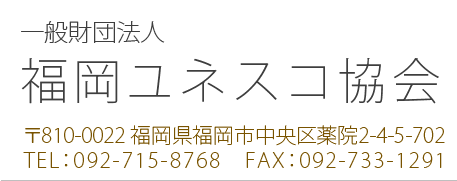第7回日本研究国際セミナー’93

Aセッション テーマ 「戦後日本の初期政治過程 - 変革と持続 -」
発表
「戦前・戦後日本政治の持続と変化」 福井治弘氏(カリフォルニア大学セントバーバラ校教授)
| (内容紹介) |
| 序 |
- 政治制度、文化、行動の3分野における変革と持続の認識
- 政治代表制度における変革と持続
- 地方政治
- 官僚制、政策決定、国家と経済社会
- 変革と持続観の変遷
- 結びにかえて:戦後日本政治変革論と近代化論
|
「55年政治体制の成立前後における保守党派閥の変化」
Steven Reed 氏(アメリカ/中央大学政策学部教授)
| (内容紹介) |
| 自民党成立前の派閥 |
|
芦田派 |
|
鳩山対吉田-民同派 |
|
忠誠か当選か? |
|
追放解除組 |
|
吉田学校 |
|
自民党以前の派閥の特徴 |
| 自民党内の派閥 |
|
初期自民党型派閥のモデル |
|
さらなる進展 |
| 連続性と変化 |
Aセッション討議
| 議長 |
: |
石田 雄氏(八千代国際大学教授) |
| ディスカッサント |
: |
五百旗頭 眞氏(神戸大学教授) |
| 討議参加者 |
: |
Aセッション発表者 |
| (討議の内容紹介) |
| 対日占領をどう考えるか |
| アメリカにおける日本研究の世代の違い |
| 日本の伝統的地層と戦後 |
| 日本特殊論とは |
| 占領による断絶 |
| 日・独占領下の比較 |
| Reed教授へのコメント |
| 派閥の首班を選任 |
| アメリカの日本政治研究者の世代の特徴 |
| 地域研究と研究費 |
| チャルマーズ・ジョンソン教授の視点など |
| 占領期と日本の自立性 |
| 日本研究における客観性を |
| 首相のブランドイメージ |
| 日本政治の汚職の現実 |
| 政治の汚職問題 |
| 東アジア時代とは |
| 制度と文化 |
| 研究資金について |
| 価値観と分析の枠組み |
| 天皇制との関連は |
| 社会科学での価値観を排す |
| 戦後民主主義の系譜とは |
Bセッション テーマ 「保守-党支配政治と官僚」
発表
「日本の首相と受動的リーダーシップ」 Kenji Hayao 氏(アメリカ/ボストンカレッジ助教授)
| (内容紹介) |
| 分析のための枠組み |
| 首相と政策決定過程 |
| 政治的リーダーシップ |
| テクノクラティックなリーダーシップ |
| 受動的リーダーシップ |
| 共鳴振動数 |
| 下から決められる共鳴振動数 |
| 上から引き上げるという首相の役割 |
| 結論 |
「保守単独政権の崩壊と今後の展望」
Kent E. Calder 氏(アメリカ/プリンストン大学教授)
Bセッション討議
| 議長 |
: |
|
内田健三氏(東海大学教授) |
| ディスカッサント |
: |
|
藪野祐三氏(九州大学教授) |
| 討議参加者 |
: |
|
Bセッション発表者 |
| (討議の内容紹介) |
| 制度を変えるということ |
| 政治学者と経済学者の相互乗り入れを |
| リーダーシップの比較 |
| 産業構造の変化と対応 |
| 付き合い型社会へ |
| コメントに答えて |
| 日本政治経済の効率化を |
| リーダーシップのタイプについて |
| 日本の伝統的政治文化 |
| リーダーシップの分類 |
| リーダーシップの役割 |
| 日本の制度固有の論理 |
| 日本の経済構造の変化とは |
| 政治の制度論をめぐって |
| 非自民政権の今後 |
| 補佐官について |
| 選挙制度について |
| 社会改革の日を |
| アジア諸国の文化との比較を |
| 東アジア研究の現状 |
Cセッション テーマ 「湾岸戦争後の日本の政治的動向」
発表
「現代日本のナショナリズム ― 新しいナショナリズムの勃興とその形態 ―」
Bruce Stronach 氏(アメリカ/国際大学准教授)
| (内容紹介) |
| 国政と国家 |
| 軍国主義 |
| 国家のアイデンティティと世界 |
「湾岸戦争と日本の政治展開」
Terry MacDougall 氏(アメリカ/スタンフォード日本センター京都日本研究センター所長、スタンフォード大学教授)
| (内容紹介) |
| 1 湾岸戦争と日米の反応 |
| 2 湾岸戦争と日本政治の混迷 |
|
国際危機管理問題 |
|
国際的な集団的安全策 |
|
リーダーシップ欠如 |
|
意識問題と相対主義 |
| 3 日本政治の展開 |
|
意識転換 |
|
孤立の危惧 |
|
政治リーダーシップ |
Cセッション討議
| 議長 |
: |
関 寛治氏(立命館大学教授) |
| ディスカッサント |
: |
桂 敬一氏(東京大学社会情報研究所教授) |
| 討議参加者 |
: |
Cセッション発表者 |
| (討議の内容紹介) |
| 戦後日本のナショナリズム論について |
| 戦後日本のマスメディアとナショナリズム-湾岸戦争を契機に- |
| 新たな日米関係の動向 |
| 日本の進路への危惧 |
| メディアにしっかりした論議を |
| メディアの役割とは |
| ポスト冷戦とアメリカとの協力 |
| 歴史の教訓から |
| アメリカが日本に求めるもの |
| 正しいナショナリズムの教育を |
| 日本の平和憲法について |
| 湾岸戦争を考える |
| 沖縄から見た日本のナショナリズム |
| ナショナリズムの両義性 |
| アメリカの日本への失望 |
総括討議
| 議長 |
: |
升味準之輔氏(東京都立大学名誉教授) |
| コメンテイター |
: |
Haruhiro Fukui (Prof. Univ. California) |
|
|
松下圭一氏(法政大学教授) |
| (総括討議の内容紹介) |
| はじめに |
| 経済的・社会的変化の重要性 |
| スキャンダルと自民党・社会党の議席の変遷 |
| 豊かさをもたらさなかった高度成長 |
| ’93年の7月選挙と地殻の変動 |
| 近代化発展過程の分析 |
| 都市型社会へ |
| 文化の二重構造 |
| 制度の二重構造 |
| A、B、Cセッションから |
| 55年自民党体制崩壊の原因 |
| 文化概念への疑問 |
| 非自民政権と国際的側面 |
| 第三の民主化の波とは |
| アメリカの日本政治研究から |
| 世界を動かす新しい情報産業 |
| 日本の持つ潜在的危険性 |
| 政治学の知的生産性の欠如 |
| 日本の再軍備心配の理由 |
| 大国の使命感に迷惑 |