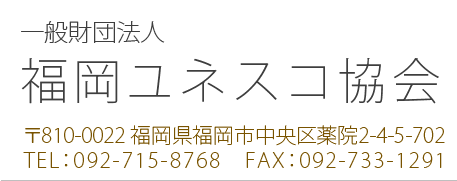「文学が描くイタリアと移民」(栗原俊秀氏講演会)を終えて
今年度の講演会はイタリア文学に関してお話をいただくことになり、翻訳家の栗原俊秀さんに「文学が描くイタリアと移民」をテーマにご登壇いただきました。
栗原さんは、京都大学を卒業した後にカラブリア大学に留学しました。そこでの現代イタリア文学の講義で読んだ作家アマーラ・ラクースの作品のテーマが移民についてだったことから、このテーマに興味を持ったそうです。ラクースは、自分自身がアルジェリア系というバックグラウンドを持つこともあり、イタリア社会における移民の生き方に強く関心を持っている作家だったそうです。
現在、イタリアには多くのアラブ系やアフリカ系など、見た目からして明らかにヨーロッパ人ではない人たちが暮らしています。ある日本人旅行者の感想文には「外国人の給仕係が多く、イタリアではないようで、どこかなじめませんでした」という記述があり、そのような状況になっているそうです。
そして、この外国人たちの境遇は、イタリアの重要な現代作家メラニア・ガイア・マッツッコが書いた小説『ビータ』に描かれている状況を連想させるといいます。その小説では「表玄関の門には、『犬、黒人、イタリア人、立ち入り禁止』と書いてあった」と述べられており、20世紀初めのニューヨークに暮らしていたイタリア系移民たちの境遇が描かれています。
このように、現代のイタリア文学だけではなく、20世紀前半にアメリカに移住したイタリア人の子孫の作家たちがアメリカで書いている作品も紹介しながら、栗原さんは次の点を説明されました。20世紀初めのアメリカでイタリア系移民が大変厳しい差別に晒されていた状況と、現在イタリアに住んでいるアラブやアフリカからの移住者の状況が類似しているということです。
これを歴史的に見ると、イタリアも日本と同様に、第二次世界大戦後に「奇跡の経済復興」という時代があり、そこで非常に豊かな国の仲間入りを果たしました。その後、アジア、アフリカ、アラブからの移民を引きつけるポジションになったのです。イタリアから外国へ旅立っていくエミグランティ(移民)の数と、外国からイタリアに入ってくるインミグランティ(移住者)の数が逆転したのは、1970年代に入ってからのことだったということです。
栗原さんが引用された作品の中で特に多かったのが、『デイゴ・レッド』というイタリア人を侮蔑する言葉をタイトルとした小説を書いたジョン・ファンテという作家の作品でした。ファンテはイタリア系アメリカ移民第二世代の、英語で書く作家で、研究者たちはこの作家の作品をイタリア系アメリカ文学について研究する上で最も重要な作家と位置づけているそうです。そして、イタリアの作家たちが非常に熱心に読んでおり、今ではアメリカ本国よりもイタリアのほうが人気があるのではないかということです。
現代イタリアの作家アマーラ・ラクースやカルミネ・アバーテの作品も詳しく紹介されました。彼らは、かつてのイタリア系移民の経験と、現代イタリアにおけるアラブ系やアフリカ系移民の状況との類似性に注目しており、「言葉と宗教と肌の色を変えただけの同じ物語」が繰り返されているという「移民の歴史の回帰性」という視点が提示されました。
講演の冒頭で語られた、栗原さん自身の翻訳家としての原点が印象的でした。
もともと研究者を志していた栗原さんが翻訳を中心に活動するようになったのは、「研究論文を書く際には文学作品を都合よく利用しているような後ろめたさがあり、むしろ作品全体を読者に届ける翻訳という仕事に魅力を感じた」からだと紹介されました。文学に対する栗原さんの誠実な姿勢とお人柄が強く伝わってくるお話でした。
BLOG
- 「内村鑑三『デンマルク国の話』を読む——大国から小国へ」を終えて
- 「老いとぼけの自由な世界~介護の先に見えること」を終えて
- 「終戦を再考する」を終えて
- 「本の未来を拓く」を終えて
- 映画『ホセ・リサール』上映とアンベス・R・オカンポ氏ビデオ講演を終えて
- 「文学が描くイタリアと移民」(栗原俊秀氏講演会)を終えて
- 「アジア映画の面白さとは何か」講演会・上映会を終えて
- 「アジアと国際秩序の現在、そして未来」(佐橋亮氏講演会)を終えて
- 「言葉は世界を変えられるか」(中島岳志氏、國分功一郎氏の講演と対話) を終えて
- 「江戸時代における長崎への画家遊学」(福岡ユネスコ・アジア文化講演会)を終えて
- 「森鷗外とドイツ文学」(美留町義雄氏講演会)を終えて
- 「往還する日・韓文化の現在」(伊東順子氏講演会)を終えて
- 「宗教・文化からみたロシアとウクライナ」(高橋沙奈美氏講演会)を終えて
- 「変わる中国、変わらない中国」(岸本美緒氏講演会)を終えて
- 「多文化共生とコミュニケーション・外国人との共生がコミュニティを豊かにする」を終えて
- 「ラテンアメリカ文学の魔力」(寺尾隆吉氏講演会)を終えて
- 「映画創作と自分革命」(石井岳龍氏講演会)を終えて
- 「大陸と日本人」(有馬学氏連続講演会)を終えて
- アジア文化講演会「生きる場所、集う場所」を終えて
- 「多文化共生を実現するために、私たちのできること」(オチャンテ・村井・ロサ・メルセデス氏講演会)を終えて
- 「『台湾』を読む」(垂水千恵氏講演会)を終えて
- 「コロナ危機以降のアジア経済」を終えて
- 「蘭学の九州」(大島明秀氏講演会)を終えて
- 「日本語を伝達ツールとして見直していく」(徳永あかね氏講演会)を終えて
- 「七つの文学作品で読む韓国社会の過去と現在」(きむ ふな氏講演会)を終えて
- 「琉球沖縄史を見る眼 〜なぜ『茶と琉球人』を書いたのか?」を終えて
- 「日本映画は中国でどのように愛されてきたのか」を終えて
- 「魯迅―松本清張―莫言 ミステリー / メタミステリーの系譜」を終えて
- 「対外関係から見た中国」を終えて
- 「「平成」とはどんな時代だったのか」を終えて
- 「北欧諸国はなぜ幸福なのか」を終えて
- 「人口減少社会 ― その可能性を考える」を終えて
- 「19世紀ロシア文学とその翻訳」を終えて
- 福岡ユネスコ・アジア文化講演会「アオザイ」を終えて
- アジアと出会う旅 ―ボクシング資料が切り拓く日本・フィリピン関係史を終えて
- 「日本(イルボン)発韓国映画の魅力を探る」を終えて
- 「アメリカをもっと深く知ってみる―なぜトランプが出てきたのか?」を終えて
- 「香港におけるアヴァンギャルド文化とその未来」を終えて
- 「文学の国フランスへのお誘い」を終えて
- 「英国のいま、そして日本は?」を終えて