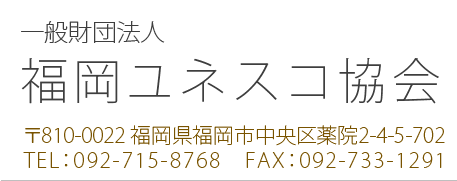「終戦を再考する」を終えて

今年が戦後80年の節目となるため、7月5日に福岡市の電気ビル共創館で「終戦を再考する」をテーマに福岡ユネスコ文化セミナーを開催しました。講師は、成城大学法学部法律学科教授の麻田雅文氏と、上智大学文学部新聞学科教授の佐藤卓己氏のお二人で、それぞれの講演と講演後に短いトークをはさみ、最後に対談という形式で、「日ソ戦争」と「終戦」について問い直す充実したセミナーとなりました。
忘れられた「日ソ戦争」
最初の講演は麻田雅文氏の「日ソ戦争(1945年)——残された負の遺産と教訓」で、1945年8月8日にソ連が宣戦布告し、翌9日から始まった日ソ戦争について詳しく語られました。この戦争は「戦後」に始まった戦争とも言えるもので、東京で宣戦布告の文書が渡された8月10日には、すでに日本政府はポツダム宣言の受諾をソ連側に申し入れていたのでした。
そして、この日ソ戦争の知名度が低い理由として、「原爆神話」と「8月15日の神話」という二つの神話が重なって見えづらくしていると指摘されました。広島・長崎への核攻撃が日本を降伏させたというストーリーや、8月15日の玉音放送で戦争が終わったという認識が、同時期に始まり9月上旬まで続いた日ソ戦争を脇に追いやってしまったのです。
国体護持のために犠牲にされたもの
麻田氏は、1945年の日本の指導者たちが何を守ろうとしたのかを、国民国家の三要件(領土・国民・主権)から分析されました。当時の日本は、領土を放棄しても、国民を犠牲にしても、「国体」すなわち天皇が国家を統治する政治システムを守ることを最優先していました。ポツダム宣言を受諾する際、日本が唯一付けた条件は「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す」というものでした。
その結果、満洲、南樺太、千島列島で多くの民間人が犠牲となりました。関東軍は作戦計画を急遽変更し、最前線の兵士たちに「陸の特攻」や玉砕戦術を強いました。南樺太では真岡郵便局の電話交換手9名が集団自決し、千島列島の占守島では激戦が繰り広げられました。
残された負の遺産
最後に、麻田氏は日ソ戦争が後世に残した負の遺産の大きさを強調されました。ソ連軍の戦死傷者は約3万6000人、日本軍は3万人以上が戦死し、シベリア抑留で約5万5000人が死亡、さらに民間人約20万人を含めると、合計30万人以上の日本人が犠牲になったと推定されています。
また、領土の喪失、中国残留孤児・残留婦人やサハリン残留コリアンの問題、北方領土問題、未返還の遺骨など、未解決の問題が数多く残されています。そして、日本では戦争の記憶が薄らいでいるのとは対照的に、中国とロシアは戦争の記憶を政治的に強化していることも指摘されました。
「終戦日」の再定義へ
『八月十五日の神話―終戦記念日のメディア学』の著者として知られている佐藤卓己氏の講演「「8月ジャーナリズム」再考——「9月ジャーナリズム」の時代へ」では、まず、「終戦日」の定義そのものが曖昧であることを指摘されました。満洲事変の終戦日を答えられる人がいないように、現代のウクライナ紛争でも終戦日の確定は困難です。8月15日は玉音放送があった日ですが、この「終戦の詔書」は日本国民に向けたもので、国際的には外交上の意味を持たない文書でした。実際、世界各国の終戦日は多様で、アメリカは9月2日、中国とロシアは9月3日、韓国は8月15日、台湾は10月25日としています。
「玉音写真」の検証
講演で特に印象的だったのは、佐藤氏が研究を始めたきっかけが福岡の九州飛行機香椎工場での玉音放送写真の調査だったことで、新聞に掲載された8月15日の「玉音写真」の多くがヤラセや修正写真であったという検証結果でした。香椎工場の写真をはじめ、『朝日新聞』大阪本社版の涙を流す少女の写真(涙が後から手書きされた)、『北海道新聞』の「玉音に嗚咽する少年たち」の写真など、いずれも戦意高揚のためのプロパガンダ写真が転用されたものでした。
なぜ8月15日が「終戦の日」となったのか
佐藤氏は、8月15日が終戦日として定着した理由を二つ挙げられました。一つは政治的理由で、屈辱的な「降伏」の9月2日より「終戦」の8月15日の方が望ましいと考えられたこと。特に、昭和天皇の英断を強調する保守派と、8月15日をもって主権が国民に移ったとする「8・15革命」を主張する進歩派の双方にとって都合が良かったという「記憶の55年体制」が形成されたとのことです。
もう一つはメディア論的理由で、降伏文書調印という官僚的な文書コミュニケーションよりも、玉音放送という大衆的なラジオ・コミュニケーションの方が、国民参加の政治儀礼として集合的記憶を作る上で有効だったということです。
「8月ジャーナリズム」から「9月ジャーナリズム」へ
佐藤氏は最後に、現在の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」を二分割し、8月15日を国内向けの「戦没者を追悼する日」、9月2日を国際的にアピールする「平和を祈念する日」とすることを提案されました。自国中心の情緒的な「8月ジャーナリズム」から、世界標準の対話的な「9月ジャーナリズム」への転換が必要であり、9月1日から18日にかけて学校の教室で戦争と平和を考える教育が望ましいと述べられました。
おわりに
両氏の講演を通じて浮かび上がったのは、「終戦」という出来事が、いかに複雑で多面的なものであったかということです。8月15日という日付は、日本国内での政治的・文化的な合意の産物であり、国際的な視点や実際の戦闘の終結とは必ずしも一致しません。
戦後80年を迎えた今、私たちは情緒的な記憶から離れ、歴史的事実に基づいた対話を始める必要があるのではないでしょうか。両氏が提起された問題は、過去を振り返るだけでなく、現代の平和と安全保障を考える上でも重要な示唆を与えてくれる講演会となりました。
BLOG
- 「老いとぼけの自由な世界~介護の先に見えること」を終えて
- 「終戦を再考する」を終えて
- 「本の未来を拓く」を終えて
- 映画『ホセ・リサール』上映とアンベス・R・オカンポ氏ビデオ講演を終えて
- 「文学が描くイタリアと移民」(栗原俊秀氏講演会)を終えて
- 「アジア映画の面白さとは何か」講演会・上映会を終えて
- 「アジアと国際秩序の現在、そして未来」(佐橋亮氏講演会)を終えて
- 「言葉は世界を変えられるか」(中島岳志氏、國分功一郎氏の講演と対話) を終えて
- 「江戸時代における長崎への画家遊学」(福岡ユネスコ・アジア文化講演会)を終えて
- 「森鷗外とドイツ文学」(美留町義雄氏講演会)を終えて
- 「往還する日・韓文化の現在」(伊東順子氏講演会)を終えて
- 「宗教・文化からみたロシアとウクライナ」(高橋沙奈美氏講演会)を終えて
- 「変わる中国、変わらない中国」(岸本美緒氏講演会)を終えて
- 「多文化共生とコミュニケーション・外国人との共生がコミュニティを豊かにする」を終えて
- 「ラテンアメリカ文学の魔力」(寺尾隆吉氏講演会)を終えて
- 「映画創作と自分革命」(石井岳龍氏講演会)を終えて
- 「大陸と日本人」(有馬学氏連続講演会)を終えて
- アジア文化講演会「生きる場所、集う場所」を終えて
- 「多文化共生を実現するために、私たちのできること」(オチャンテ・村井・ロサ・メルセデス氏講演会)を終えて
- 「『台湾』を読む」(垂水千恵氏講演会)を終えて
- 「コロナ危機以降のアジア経済」を終えて
- 「蘭学の九州」(大島明秀氏講演会)を終えて
- 「日本語を伝達ツールとして見直していく」(徳永あかね氏講演会)を終えて
- 「七つの文学作品で読む韓国社会の過去と現在」(きむ ふな氏講演会)を終えて
- 「琉球沖縄史を見る眼 〜なぜ『茶と琉球人』を書いたのか?」を終えて
- 「日本映画は中国でどのように愛されてきたのか」を終えて
- 「魯迅―松本清張―莫言 ミステリー / メタミステリーの系譜」を終えて
- 「対外関係から見た中国」を終えて
- 「「平成」とはどんな時代だったのか」を終えて
- 「北欧諸国はなぜ幸福なのか」を終えて
- 「人口減少社会 ― その可能性を考える」を終えて
- 「19世紀ロシア文学とその翻訳」を終えて
- 福岡ユネスコ・アジア文化講演会「アオザイ」を終えて
- アジアと出会う旅 ―ボクシング資料が切り拓く日本・フィリピン関係史を終えて
- 「日本(イルボン)発韓国映画の魅力を探る」を終えて
- 「アメリカをもっと深く知ってみる―なぜトランプが出てきたのか?」を終えて
- 「香港におけるアヴァンギャルド文化とその未来」を終えて
- 「文学の国フランスへのお誘い」を終えて
- 「英国のいま、そして日本は?」を終えて
- 「言葉でアジアを描く―現代文学とアジア」を終えて